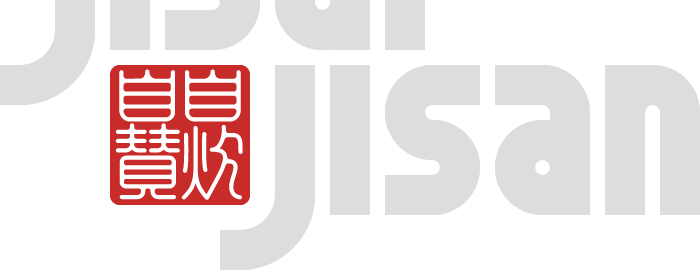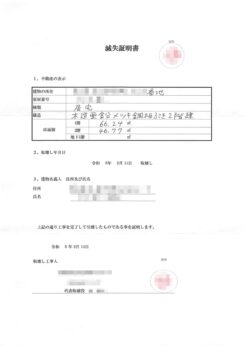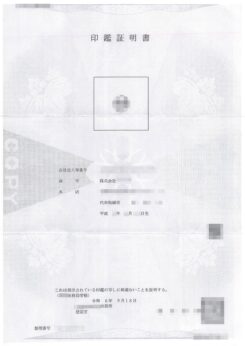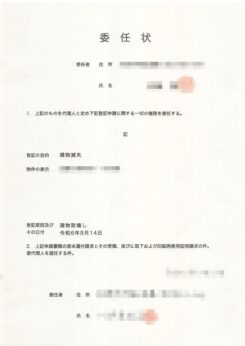2年前に義父が他界。
相続にまつわる手続きの諸々を私が手伝っておこなったのだが、不動産の相続登記については先延ばしにしていた。
相続登記とは、亡くなった人の持っていた土地や建物をその家族の誰かの名前に変更する手続きのこと。
土地や建物を誰が持っているかは役所(この場合は法務局)でその情報を記録する。この記録を「登記」という。なので「相続登記」なわけですね。
先延ばしにしていたのは、とりあえず不都合はなかったし、その時点では特に罰則等もなかったから。
それが、法律が変わって…
令和6年4月1日以降、相続等で不動産の所有権を取得した相続人等は、「自己のために相続が開始したことを知り」なおかつ「その不動産の所有権の取得を知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなくてはならない(不動産登記法第76条の2)。
ということになった。
これを怠ったままにしていると、罰則もあるという(不動産登記法第164条)。
経緯は後述するが、相続した家を解体することになったし、そろそろやるしかないかと思い、自分でやってみたら思ったより簡単だったので、必要な誰かのために情報を共有。
相続した不動産に土地はなく家だけ
相続したその不動産は義父と義母が二人で住んでいた家だけ。土地は借地である。

戸建住宅のイメージ画像。この記事の物件とは関係ありません。
高齢の義母が戸建てに一人で住み続けるのも何かと不便且つ不安なので、利便の良い集合住宅に転居。土地は地主に返すこととなった。
地主との契約では契約終了時には家を解体して更地にすることになっていた。家を売却して買主が契約を継承するということでもかまわないということだったのだが、土地なし家だけというのはなかなか買い手がつかないものなのだ。解体費用もかかるのでタダで譲ってもよかったのだが、結局貰い手も見つからなかった。
そういうわけで、転居後、家は解体ということになった。
家を解体するとなれば、家がなくなったことを登記する「滅失登記」も必要になってくる。
「相続登記」をしてから「滅失登記」だなあ。と考えながら調べていたら…
相続した家を解体するなら滅失登記だけでいい
家を解体するなら、相続登記をしていなくても滅失登記をするだけで良いということがわかった。
危ない危ない、知らないでいたら余計な手間と出費がかさむところだった。あわてて相続登記しないでいて良かった!
登記の手続きは土地家屋調査士に代行を依頼することができる。相場は3〜5万円くらいだという。しかし、不動産の相続登記以外の相続の手続きが終了しているなら、あとは全然難しくない。
必要な書類を揃えて管轄の法務局で手続きをする。書類が揃っていれば郵送するだけで続きを完了することも可能だ。
用意する書類
相続した家の登記がまだで滅失登記をする場合に必要な書類は下記のとおり。
建物滅失証明書
通常、建物の解体を請け負った業者が解体完了時に作成してくれる。念の為工事を契約する際に確認しておこう。
これを作成してくれないような業者には依頼しないのが賢明。
解体業者の登記事項証明書と印鑑証明書
「解体業者の登記事項証明書」とは解体業者の資格を証明する書類。会社法人等番号を記載すれば、添付を省略できる。
印鑑証明書に会社法人等番号が記載されている場合にはその印鑑証明書だけで良い。
建物滅失登記の申請書
法務局が公開している書式(法務局:滅失登記申請書書式)を用いて作成する。記入例はこちら→「法務局:滅失登記申請書記入例」
相続関係を証明する書類
申請者が解体した建物の相続人であることを証明する書類。相続人が複数いる場合でも申請者だけの証明で良い。←これ重要、ただし相続人間で合意しておかないと後々トラブルになるので注意。
他の相続手続きの際にあらかじめ多めに取得してとってあればそれらをそのまま利用できる。一般的には下記の書類がそれらにあたる。
- 被相続者の戸籍謄本
- 被相続者の改製原戸籍謄本(かいせいはらこせきとうほん)
- 相続者の住民票
申請者が相続時以降転居していたら申請者の住民票は新たに取得する必要がある。
その他
委任状
相続人が高齢で本人が手続きすることが難しくて家族が代理で申請するということも多いと思う。そういう場合は委任状が必要。
登記事項証明書(不要)
ネットで検索していると、上記の他に、「登記事項証明書」が必要とする情報もあるが、実際は必要なかった。
管轄の法務局(出張所)に電話して確認したので間違いない(その後、登記も完了しているし)。
法務局の担当曰く、「それは、こちらではわかっている内容なので必要ないですよ〜」
ただし、登記簿の写しなどが保管されておらず、相続した物件がどれで、そうでないのがどれなのかなど、詳細が判然としていない場合には必要になるかもしれない…
けれど、要は滅失証明書に記載する地番と家屋番号とその所有者がわかれば良いのであって、そもそも地番と家屋番号がわからないと滅失証明書も作成できない。
「地番」とは「住所」とは全く別で、法務関係の手続きでも用いられる土地の番地。「家屋番号」も同様に法務関係で用いられる建物の識別番号。ふだん目にすることはほとんどないけれど、家屋・土地を所有していたなら毎年きちんと固定資産税を払っていたはずで、そうであれば、その納税通知書に記載されているのでわかるはず。
納税通知書は処分してしまってないということなら、管轄の法務局に電話して問い合わせるのが一つの方法。最近になって管轄の法務局に電話すれば教えてもらえるようになったとのこと→「地番を調べる方法はありますか」(管轄の法務局とは最寄りの法務局ではなく、解体する家の住所地を管轄する法務局なので間違いがないよう注意)。
その他にも申請方法について疑問があれば、管轄の法務局に電話すると、わりと親切に教えてくれるのでおすすめだ。→「法務局:管轄のご案内」
ただし、どの法務局も親切かどうかは保証しない。
申請方法
管轄の法務局が近くにあって気軽に行き来できるなら準備した書類を持って直接出向いて申請するのがおすすめ(「管轄の法務局」とは上述した通り、解体した家の住所地を管轄する法務局のことなので注意)。
窓口で不備が見つかった場合、訂正用の印鑑を持っておくとその場で修正して再提出できるケースがあるため便利。
管轄の法務局が離れた場所にあるなら、郵送でも良い。その際は「不動産登記申請書在中」と表書きし、登記完了証を返送してもらうための自分宛の封筒と書留用の切手を同封し、受け取り確認ができる簡易書留などで郵送する。筆者の場合は、レターパックプラスを用いた。
ちなみに、「滅失登記」の手続きそれ自体に費用はかからない。申請に必要な書類(上述の住民票その他)を取得するための費用や、郵送料や交通費などの実費のみだ。
相続登記の場合には、登録免許税という税金が、不動産の評価額に応じて必要になるので、その点でも、相続登記を省いて滅失登記をするのが断然お得なのだ。
まとめ
筆者の場合、郵送(レターパックプラス)で申請、2週間ほどで登録完了証が届いた。
筆者の場合、事前に何度か電話で確認していたので特に不備もなく1回の郵送で完了したが、不備があった場合にはあとから窓口へ行って訂正するか郵送で再提出することになる。
自信がない場合は事前に電話で相談するのがおすすめ→「法務局:管轄のご案内」
最後に、Macユーザー限定で、今回自分用に作成たPages形式の「建物滅失登記の申請書」と「委任状」を雛形にして公開します。
どなたかのお役に立てば。